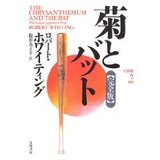もうじき、うちの学生の2年生は課題研究(通常の卒論)の中間発表を迎える。今年は2名の学生を持つが、毎年のことだが、発表資料を出されると「うーん」と思うことがある。
指導を受ける学生は、物事を難しく考えすぎだ。100を調べたら100のことを全て盛り込みたいと考える。そうすると、問題は大事な話の筋道を忘れて細かいことに走りすぎ、物事の論理が通らなくなり、私に怒られることとなる。
課題研究の発表とは、観光客が、バスガイドに案内されて世界遺産をまわると思えば考えやすい(?)。バスガイドは発表者、観光客が聞き手だ。
私の周りにもすばらしい発表をする人がいる。その方は、難しい概念も中学生にもわかるように簡単に説明する。神業だ。だから、異分野の私でも非常に参考になる知見を得ることができる。これはまねしてまねできるものではない。まして初心者には無理だ。私の要求はそれではない。
人に説明して分かってもらうことは、裏を返せば、いままで分からなかったことが分かるようになってもらうことだ。そこで重要なのは、論理、つまり話の筋道だ。人は論理で考え、論理的に腑に落ちたものを直感で分かる。(日ごろから問題意識がある人は、論理は必要なく、腑に落ちたもので分かるにいたる。その場合は、彼は人にそれを説明することができないが・・・)。
日ごろから、あることに問題意識のある人は、つねにそれにかんする周辺情報を身近に覚えている。けれども、あることが分からないのは、「キー」がないからだ。だから周辺知識が有機的に結びつかず、分からないままだ。そんなわけだから、日ごろから問題意識を持っている人にとって、人の発表に必要なのは「キー」を得ることだ。話の道筋はどうでもいい。単語単位でキーを捜しながら話を聞く。一方、日ごろから問題意識を持っていない人にとって、誰かが(発表者)毎日考え続けて結論に至ったことが分かるためには、「手取り」「足取り」説明をしなければならない。その説明に必要なものが論理、話の筋道だ。なぜ、その話が重要なのかから始まって・・・。だから難しい話は必要ない。もちろん、例外はあるが、そんなのは【質問」されたときにこたえればいい、それくらいの気持ちだ。
うちの学校の課題研究などはまさに、それだ。皆専門がバラバラ。だからそれぞれが個別に取り組んでいることなど理解できない。となると、学生さんに必要なのは、自分のやっていることを中学生に説明するのと同じだ。難しく考えることはない。
「空手バカ一代」の中にこんな会話がある。「実践では、こんなことはありえないのに、どうして、そんな練習をしないといけないのか」(とび蹴りの練習をするときにはるかに頭よりも高い位置のボールをける練習をするときの会話)。大山曰く「実践では練習の数十パーセントのことしかできない。つまり実践よりも高いレベルが実行できないものが、どうして実践で力を発揮できるのか」。
また、こんな会話をパラリンピックの報道で知った「本番で楽になるためには、練習では本番以上の辛い練習をしないといけない」
また、最近あった北海道女子マラソンの優勝者が恩師の小出監督から言われたことをいっていた。「練習でできなことは本番でできないんだよ」。
つまり、発表という本番は、本番。しかし、そこにいたるまでは発表することの数十パーセント深く調べていないといけないということに通じる意見。それぞれの上の会話は私はそのとおりだと思う。
うちの学生に望むのは、業界では説明すれば業界人にもわかることを、中学生にもわかるように説明するように発表に道筋を考えてほしいということ。そんなに難しいことではない。