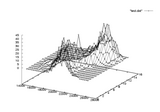話はさかのぼること昨年。修理にだしていたデジタルカメラが年末に戻ってきた。その一方で、正月休みは職場が全館閉鎖になり、デジタルカメラから画像を取り出す道具をとりにいけなかった。そのため、せっかく写真を撮ったのだが、それらの写真をブログにアップすることができない。その結果、年末から新年にかけての行動をブログにアップする機会を失った。これから何話か過去の話が登場することになる。ご容赦を。
話はさかのぼること昨年。修理にだしていたデジタルカメラが年末に戻ってきた。その一方で、正月休みは職場が全館閉鎖になり、デジタルカメラから画像を取り出す道具をとりにいけなかった。そのため、せっかく写真を撮ったのだが、それらの写真をブログにアップすることができない。その結果、年末から新年にかけての行動をブログにアップする機会を失った。これから何話か過去の話が登場することになる。ご容赦を。
10月9日のブログに研究目的で「ボート」を購入したと書いた。また、12月15日に2馬力の船外機を購入したとも書いた。ボートと船外機を自分の物にしたにもかかわらず、購入した(オークション)梱包さえ解いておらず、中身の確認さえしていない。これではダメだ。なぜなら、正月に「ボート」の走行テスト(速度・スピード・耐久性)をしようとしているからだ。そこで12月29日、研究機材を置いてある職場から前日に機材を持って帰り、29日は長良川での走行テスト(機材チェック)をすることにした。ところが、単にゴムボートを膨らませ、静水にうかべるだけではつまらない。そのため、家の裏(長良橋)から千鳥橋まで繰り出すことにした。およそ5・6キロ。この距離なら、正月に予定している「走行テスト」のフィールドの予行演習にもなるハズだ。あーして、こーして、こんなとき・・・。いろいろ頭でシュミレーションしたが、川での出来事だ。簡単、簡単・・・。

まずボートの梱包を解く。電動ポンプが入っていた。ウシシ、こいつは楽だ。手元にバッテリーも沢山ある。ボートの空気入れ、これで、大体いつも汗びっしょりになる。それから開放!・・・とおもったが、あまりにも非力だった。話にならん。そこで手動ポンプで空気を入れる。
おっと、穴も開いていない。少々小さめだが、丈夫そうなボートだ。
次は船外機、オイルを入れて・・・。
ボートと船外機をセットアップ。うーん、マイボート。いい感じだ。それっ、進水式!レッツゴー。
 うーん、なんだかスピードがいまいち乗らない・・・。ボートの底の形が以前、メーカーから提供してもらったボートと違うことがそんなにスピードに影響するのだろうか・・・。それとも気のせいか・・・?しかし、長良川を逆流しているときのスピードは手元のGPSでは時速6キロ。まぁ、こんなものなのか・・・。少々不満ではあったが、滑り出しは好調。
うーん、なんだかスピードがいまいち乗らない・・・。ボートの底の形が以前、メーカーから提供してもらったボートと違うことがそんなにスピードに影響するのだろうか・・・。それとも気のせいか・・・?しかし、長良川を逆流しているときのスピードは手元のGPSでは時速6キロ。まぁ、こんなものなのか・・・。少々不満ではあったが、滑り出しは好調。
ところが、事件は最初の瀬で起きた。
岐阜市は県庁所在地でありながら、そこを流れる長良川の水はキレイで、しかも白波の瀬がある。そこが岐阜市の長良川の魅力だ。この瀬、見ている分には楽しいが、船に乗ってみるとかなりきわどいことが今回わかった。時速6キロ程度の推進力では瀬を遡れなかった。いままで何度かその場所を川くだりしているが、瀬はあっという間に終わってしまう楽しいところ、それくらいの感想しかなかった。ところが、遡ろうとして近づくと、ショウもない小さな瀬でさえ、明らかに断層かなにかの段差がある。登山するときに斜面を見上げる、そんな感じの圧迫感だ。
しかも石だらけ、水深は浅く、船外機のプロペラが石にあたり、破損しそう。
私はここでやっと後悔した。長靴、もしくはサンダル(水はとても冷たいが)にしとけばよかった・・・。私は、簡単に考え、長靴は職場においてきたし・・・、しかし、買うほどのこともない。まぁ、皮のエンジニアブーツでも水につかることはあるまい。そう思って、皮のブーツで乗船。しかし、この瀬が越えられない今、撤退か継続か・・・。判断の分かれ道にきた。私は継続を選択した。
船から降り、船を川から引き上げ、船外機をはずし、ボートと船外機を別々に担いで瀬を越した。この川原でボートや船外機を担ぎながら、重さにあえいでいる私は「植村直己さんの北極点のときの苦労に比べれば、いまの苦労なんて、鼻くそみたいなもの」と自分を奮い立たせ、汗をかきながら荷物を運んだ。このとき、エンジニアブーツはまだ、長靴のような働きをしてくれた。
再度ボートをセットアップして川に乗り出す、するとすぐに、また小さな浅い瀬。こんな瀬・・・と思って直進したが、エンジンフル回転であるのに川に流され始める。あれ・・・。思い当たる節がある。ヒマラヤでも起きた。スクリューと本体をとめる金具が、スクリューが石にあたったときに破損したのだ。
しまった、簡単に考えていたので工具を持ってきていない・・・。しかし、手持ちの車の鍵とキーホルダーを使いなんとか部品交換できた。
再出発。100mいかない間に、また同じ症状・・・。またスクリューを石にぶつけて・・・。しかし、その過程でやけくそになり、エンジニアブーツが長靴代わりになり、さらに、やけくそ度がパワーアップしてエンジニアブーツの中に水がガボガボ入りながら、自分も汗と水でびしょぬれになりながら、がんばったのだが・・・。
・・・今回のテストはこれでギブアップ。走行距離1.4キロほど。結局、長良橋から鵜飼大橋までしかいけなかった。