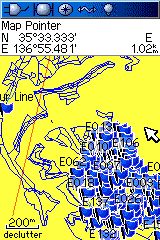どうやら山火事は自然発火ではなさそうだ。はっきりしたことは素人の私が判断するのもなんだが、どうも、メガライスプロジェクトによって森林伐採がされた後に、生えてきた藪を焼き払い畑にするために、人が燃やしているように思えた。
ある村の村長を訪問したときにいろいろわかった。
それにはインドネシアの国情を簡単に知る必要がある。
インドネシアの人口は現在約2億人。そしてジャカルタはアジアでも最大の都市。このところの医療の発達で死亡率は下がり、人口が急増。特に、ジャカルタのあるジャワ島では、ジャワ人の人口増加が著しい。通常、このように発展途上国で人口が増えれば、その人口は耕作地で養いうる人口を超えれば、都市に仕事をもとめ人口の移動が起こる。そして、職にあぶれた人が都市の周辺にスラムを作る。また村の少女は都市に売られていく。日本でも東北と上野周辺はかつてのそれだった。
さて、インドネシア。ジャワ島で増えすぎた人口にたいしてインドネシアがとった政策は移住・入植だった。その入植先が中部カリマンタン。私が訪問した土地だった。
インドネシアでの入植は次の条件で行われている。
入植した人に対して、1ヘクタールの土地と住居が与えられ、一年間の食料が保障される。その一年の間にちゃんと食料を自給できるようにせよということだ。そこで、生活の基盤を立てられれば、都会のスラムに行くことなく”独立世帯”になれる。
一方、土地の悪い泥炭のに入植したものは5ヘクタールの土地と住居、5年間の食料が保障される。5年の間に自立できれば、”独立世帯”である。スラムに行く必要なない。
写真のおばはんは、畑でジャガイモ・とうもろこし・ナス・米・・・などを作っているといっていた。

子供たちは、親たちの入植の苦労も考え及ばず、元気に遊んでいる。
親たちは子供たちを食べさせるために、一生懸命畑を開墾している。

日本が明治時代、北海道に入植したのを思い出した。
また、岐阜の山村に入植した人々の苦労話を思い出した。
そして、いまではそれらは美談の1つとして、思い出されている。
また日本は、ブラジルへ入植団を送っている。
ハワイへも送っている。
そして、サイパン・テニアンでの万太郎たちの苦労を思い出した。
大東亜共栄圏の発想は、日本で増えすぎた人口を養うため、東アジア・東南アジアの外国の植民地から外国を追っ払い、アジア諸国へ日本人を送り込み、日本への物資の安定供給を目指しながら、アジア諸国とともに発展しようというものだった。
それを思えば、インドネシアは他国に攻め入ることなく、自国の資源の中でやりくりし、この増えた人口を養おうとしている。入植した人々は村をつくるが、その村にも電気はほとんど裸電球があるだけで、夜は真っ暗な、街灯・ネオン・コンビニなど深夜もこうこうと電気を浪費している先進国などとは比べ物にならないくらいのつつましい生活だ。
しかもイスラム教徒の彼らは信心深く、確かに私たちが訪問したときは、イスラムの断食期間の終わりとその後の祭りの始まりだったことには違いないが、それでも朝の午前2時半から夜の9時半までほとんど常にコーランが大音響で村中にこだます。



また、それだけではない。インドネシアの中部カリマンタンにはジャワ人ではない先住民がいた。ダヤックと呼ばれる人たちだ。宗教もイスラムではなく、生活スタイルもジャワ人とは大いに違う。
漁をして暮らしを立てている人々。壊れかけた掘っ立て小屋で生活している。2・3の世帯で村を作っている団体もある。かと思えば、ポツンと道もなにもない、唯一船が外界との移動手段であるところに、夫婦と子供だけで生活している家族もある。ここには電気もない。あるのは家族だけ。


私にはインドネシアの中部カリマンタンで火をつけ、畑を開拓する人々は、ただ明日も家族と食卓を囲めることだけに、一生懸命に荒廃した土地と戦い、自立しようとしているだけに思った。