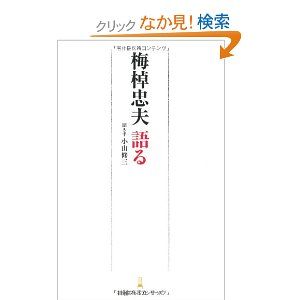
昨日、職場に行く途中、職場近くにできた巨大スーパーにバイクいじりようの手袋を買いにいった。そのスーパーには本屋もあるので、本屋の特徴をしっておこうと足を踏み入れた。
「もしも・・・ドラッカーを読んだら」だとか「スティーブジョブズ驚異のプレゼンテーション」はよく売れているようだ。そんな売れている本の中に、「写真の本を見つけた」。『梅棹忠夫 語る』である。
高校の現代社会の時間だったか、地理の時間だったか、目の見えない大阪万博跡地にできた国立民族博物館館長ということで、その人の名前を知った。とくに著作を読むわけではなかったが、転機は留年した大学5年生のときにやってきた。
タイの森林面積がどうかわって、経済がどう伸びたか?そんなことを卒論でやっていたので、タイ関連の本を読みまくった。そして偶然手にした二冊『東南アジア紀行 上・下』。これが面白かった。内容もそうだが、文章が素敵だった。こんな文章がかけたらなぁ~。そんな一冊だった。
しかも、『日本語の作文技術』という本を書いている本多勝一の文章は、梅棹忠夫の「モゴール族探検記」を目標にしていることもしった。
その後梅棹の本を読みまくり、大きな影響を受けた。
こんなこともやった。梅棹忠夫のような文章を書きたいとおもったが、そんなものはできるわけではない。だからせめて・・・と思い、会社員時代『東南アジア紀行』を一冊、原稿用紙に万年筆で書き写した。また「サバンナの日記」という本は、本の構成を図にして、梅棹の文章の書き方の特徴を必死になって見つけようとした。
そんな梅棹さんだが、昨年7月90歳でなくなった。
この本は、なくなる直前までの聞き取りをまとめた本だ。本屋では問答無用で購入。
昨晩、あっという間に読めた。
たしかに、言っていることはとても共感できることばかりだが、他の本人の著書をよんだときに受けた、「おーーそうか!」というのはなかった。しかし、アマゾンの書評を見てみたら絶賛している人が多かった。この本が売れて絶賛される理由はなんだろう。
