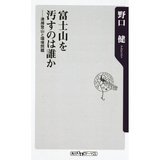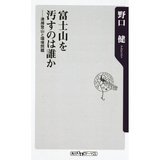 前のブログで、ネパール・カトマンズのホテルで野口健さんにあって立ち話をしたといった。あの時、彼から名詞をいただいたが、私は名詞をホテルの部屋においていたため、名詞を渡せなかった。そこで日本に帰ってきてから、「名詞をいただきっぱなしで失礼しました」と一筆書いた。
前のブログで、ネパール・カトマンズのホテルで野口健さんにあって立ち話をしたといった。あの時、彼から名詞をいただいたが、私は名詞をホテルの部屋においていたため、名詞を渡せなかった。そこで日本に帰ってきてから、「名詞をいただきっぱなしで失礼しました」と一筆書いた。
野口健。いろんな見方をする人がいる。私の周りにいる山登りや学者系統の人で彼のことをよく言う人は聞いたことがない。その一方で、彼のことを悪くいう人も聞いたことない。ただ、彼らは、ちょっと含み笑いをしながら「○○だというじゃない」と彼のことをあれこれマイナス評価しているようなニュアンスの発言をする。
一方、一般人の多くは「山登りにチャレンジし、清掃登山などもしながら、ユーモアーたっぷりで割りと好印象」という人が多い。
さて、私はどう思っているか。本人は自分の肩書きを「冒険家」「アルピニスト」と書いているが、それが「本気」なのか「お茶目なギャグ」なのか「そうせざるを得ない社会で仕方なしに・・・」なのか不思議に思っている。また、「植村直己」に影響を受け・・・なんていって、自分が植村ファンの代表のようにいうが(私が勝手に解釈しているだけだが)、植村ファンの私はジェラシーを感じる。それ以外は、いたって一般人と同じ感覚だ。
とにかく、時代の寵児となって多忙な人であることは間違いない。
そんな彼から金曜日、手紙をもらった。写真の本にサインを入れて。
(余談だが、人からサインをもらうのは好きではない。サインをねだるということは手の届かぬ存在の人だから、そのサインがありがたいのであろう。だから、サインをもらった時点で私はその人に負けたことになる!と思っているからだ。その道の有名人といわれる人にあってもサインなどねだったことはない。しかし、勝手にサインをくれた人もいる。そんなサインで唯一、私の中でありがたく頂戴しているのは「植村公子」さん。そう植村直己さんの奥さんからのサインだけ。今回、まいった。野口さんにしてやられた・・・)
職場で受け取ったとき、多忙な中お手紙つきでいただいたその本だったが、あまり読もうという気はなかった。以前聞いた講演と内容が重複していたからだ。が、寝る前、目次に目を通していたら「イムジャ氷河湖」について書かれたページがあるのを発見。そこで、イムジャ氷河湖のページを読んでみた。私達のことは2行程度のことだった。そんな中、ぺらぺらめくっていたら、写真が目に付いたページがあった。そこの記事を読んでいたら・・・。そんなことでパラパラ見ていたら読み終えてしまった。
読み終わっての感想。前述、登山をする人、学者の人のコメントである「富士山清掃なんて綺麗ごとをいっているけれど、本人はぜんぜんごみ拾いしていないというじゃないか・・・」だとか「野口健、登山家ねぇ~」であるが、それをいう人は根性が曲がっているように思えた。あの本を読んで分かったことは「たとえ、野口健がごみ拾いをしていなくても、仕掛けたのは彼で、その運動を続けているのも彼だ。活動の原動力は彼だ。だったら、ごみ拾いしていなくたって野口健は清掃登山している、富士清掃しているといってもいいではないか。それを確信した。
そんなことを言っていたら、岐阜城を作った織田信長は自分が大工になってカンナをかけて釘をうって城をつくらなければならない。誰もが岐阜城は織田信長が作った、というではないか。それと一緒。ごみを拾わなければ、ごみ拾いをしていますと公言できないなら、それはヒガミ根性以外のなにものでもない。
ところで、私は趣味は?と聞かれると、時々「自分の限界にチャレンジすること」と言うことがある。野口健の本にこう書いてあった。
『登山についていえば、趣味として今日のような登山スタイルを確立したのはヨーロッパ、なかでもイギリスの貴族クラス。限界に挑戦することにロマンを感じ、あちこちに探検や冒険に出かける』とあった。
ウヒヒ、そうか。俺はイギリスの貴族クラスと精神構造は同じか!?・・・。
 先日も書いたが、いまヒマラヤの報告書を書いている。その一環でヒマラヤにおいてきたフィールドサーバーというコンピュータが送ってくるヒマラヤイムジャ湖の映像を最近時々みている。左の写真は、2008年10月17日午前11時(日本時間)の映像だ。まだ湖は凍っていない。氷河の末端から崩れた氷山が湖の反対側まで移動してきている。
先日も書いたが、いまヒマラヤの報告書を書いている。その一環でヒマラヤにおいてきたフィールドサーバーというコンピュータが送ってくるヒマラヤイムジャ湖の映像を最近時々みている。左の写真は、2008年10月17日午前11時(日本時間)の映像だ。まだ湖は凍っていない。氷河の末端から崩れた氷山が湖の反対側まで移動してきている。 そこから、9時間の間、イムジャ湖とナムチェバザールとのインターネット回線が切断され(日中は水蒸気のせいで途切れるらしい)、次の映像が送られてきたのが午後8時(日本時間:現地時間は日本時間からマイナ3時間45分)。そのときには、ほとんど全ての流氷が溶けている。驚きの様相だ!
そこから、9時間の間、イムジャ湖とナムチェバザールとのインターネット回線が切断され(日中は水蒸気のせいで途切れるらしい)、次の映像が送られてきたのが午後8時(日本時間:現地時間は日本時間からマイナ3時間45分)。そのときには、ほとんど全ての流氷が溶けている。驚きの様相だ!