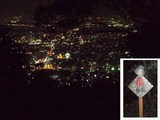よせばいいのに・・・。新金華山物語をはじめることにした。実は望遠鏡を買うための目標だとかいって、夏に金華山を30往復することにしたが、それには、大きな背景があった。この秋、ヒマラヤへの調査に誘われていたのだ。当初、そんな20日も仕事を休めないのでと、あきらめていたのだが、ヒマラヤもエベレスト山麓ということで、なんとかいけたらと環境を整えていた。そしたら職場の理解もあり、昨日どうやら、今月下旬エベレスト山麓(5000~6000m)の氷河の調査(地球温暖化にともなう氷河の後退に関する調査研究)に参加できることになった。というわけで、これまでは可能性は低いかもしれないけれど、参加可能になったときに十分働ける備えをするために、金華山に夏に登っていた。苦しみながら・・・。しかし、おかげで山登りはだいぶ楽になった。しかし、問題がないわけではない。
よせばいいのに・・・。新金華山物語をはじめることにした。実は望遠鏡を買うための目標だとかいって、夏に金華山を30往復することにしたが、それには、大きな背景があった。この秋、ヒマラヤへの調査に誘われていたのだ。当初、そんな20日も仕事を休めないのでと、あきらめていたのだが、ヒマラヤもエベレスト山麓ということで、なんとかいけたらと環境を整えていた。そしたら職場の理解もあり、昨日どうやら、今月下旬エベレスト山麓(5000~6000m)の氷河の調査(地球温暖化にともなう氷河の後退に関する調査研究)に参加できることになった。というわけで、これまでは可能性は低いかもしれないけれど、参加可能になったときに十分働ける備えをするために、金華山に夏に登っていた。苦しみながら・・・。しかし、おかげで山登りはだいぶ楽になった。しかし、問題がないわけではない。
金華山に登るとき、第一回目は水筒500ml一本リュックに入れていた。しかし、2日目から、水だって我慢すれば飲まずにすむことを発見。しかも、どうしても水が飲みたければ山頂に水道もある。だから、金華山登山は空身(からみ)でやっていた。しかし、今回の調査は調査地まで歩いて一週間かかる。しかも標高は2800~6000mの移動。これを空身で行くわけにはいかない。相応の荷物を担いでいないといけない。
というわけで、金華山物語第一章はとにかく30往復がテーマであったが、今日から出発までの約一月は「体に負荷をかける」をテーマにして、金華山登山を再スタートさせることにした。
そこで思いついたのは、無意味に荷物を背負って山に登ることである。昨年、今年ニュージーランドのトンガリロクロッシングにチャレンジしようとしていた。結局、2年連続悪天候に阻まれこのトレッキングはできなかった。しかし、そのトレッキングで「水を2リットル」つまり2キロの水を担ぐことに尻込みしたという恥ずかしい経験がある。が、今回のヒマラヤはそんなことはいっていられない。空気は薄い、高山病の心配、2キロで尻込みしているような体力では生還できない。そこで、写真のように丸太を担いで無意味に山に登ることにする。今日は10キロ(背負子を含め)であったが、出発前までにはなんとか20キロくらいを担いで登るように徐々にオモリを増やしていけたらと思う。
ところが、そんな無意味なオモリを背負っての登山。どう考えても変態である。すれ違うひとが「首をかしげ」、あの人、頭おかしいのではないか・・・などとおもうにち違いない。どう考えても恥ずかしい。そこで、人目につかないよう、夜登山をさっきしてきた。
今日の収穫は2つあった。一つはライトアップされた岐阜城は11時に消灯であるが、その瞬間を現場で立ち会ったことである。下からみていたら、ブレーカーが落ちるように「バチッ」っといってライトが消えるような気がしていたが、実際はなんの音もしなかった。またライトが光っているうちは秋の虫がないているが、ライトが消える瞬間は秋の虫が一瞬息を呑むように静寂ができるのかとおもったが、そんなことはお構いなしに、虫の音は続いていた。さらに、誰かが消しているのかな、消した後ロープウェイで降りてくるのかな、などと思っていたが、タイマーで消えているようだった。(でもそのタイマー、どうも3分遅れている)これが収穫1。
二つ目の収穫は金華山の下のほうまで降りてきて、町の光が時おり木々を通して登山道にもれてくるようになってきたとき、斜面で光る物体を発見したことだ。あかりは、ちょうど蛍のような光だった。この季節に蛍はいないが・・・。と思い考えてみた。きっと葉の上の水滴が街の光でたまたま光っているのだろうと思い、水滴を確認しようとライトを近づける。水滴はみえない。気のせいかとおもいライトをけしてしばらく暗闇を見ていると、やっぱり蛍の光。これは何だろう?光はゆっくり動く。光は明かりを増減させている。なんじゃコイツは?落ち武者の魂か・・・。それにしてはやけに小さい人魂だ・・・。他の光も近くで発見。ライトを近づけて調べてみたら、どうやら、テントウムシの幼虫のようなかっこをした体調1.5cmくらいの芋虫だった。その芋虫が光っていたのだ。下山途中、あちこちにその芋虫がいた。初めて見た!この虫の名前なんだろう。下山途中、仮の名前をつけてみた。源氏ボタル、平家ボタルを改変し岐阜城にちなみ「斉藤・織田ボタル」。