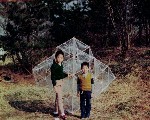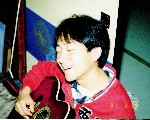木皮編/竹細工編/木工編/肉体修業編/チャーハン編/ギター編
●ひさしぶりの竹籠
冬から初春にかけて竹細工をすることが多かった。しかしニュージーランドから戻ってからは、学期の始まりでなかなか竹細工どころではなかった。
先々週に仕事も一段落したので、ひさしぶりに竹を扱ってみた。素材は、気分転換に竹を加工していたものをつかった。
つくろうとするものは、背負う籠。山に行くとき弁当・水筒・救急用品などを入れる小さめの籠。まずは、久しぶりに感触を確かめるため、また、新しいチャレンジ(籠の縁の持つところ)。

うえの籠をつくって上機嫌。しかし、籠の編み目の大きさが微妙に違うのが判る。それと予期していたよりも大きくなってしまった。
そこで今回はわりと本気で、竹の外側の部分をつかって魂をこめて作ってみた。さらに上機嫌。わっはっは・・・。
足が写っているが、倒れるからではない。大きさを示すため。サイズも、カタチも仕上がりも80点。欲を言えば、底のカタチがちょっと歪んでいる。
しかし、目の大きさや縁の仕上がりはこれまでで最高。
目指せ、原付通勤しながら竹籠を背負い。籠の中にパソコンなどの仕事道具を入れて、長良川沿いをスローに行く!!

●竹細工 四つ目編み ちょっとだけマスター
失敗し続けている四つ目編み今度こそはとおもいチャレンジした。上がアサリ拾いようのカゴ(ちょっと小さい:実用ということ口は紐で結ぶ)
下が失敗したもの(アサリカゴのミニをつくりたかったが・・・、まったくダメ)。予期せぬ形になった。ヒゴづくりは手早くできるようになった。
半日もあれば、四つ目カゴも六つ目カゴもランドセルくらいのものなら、竹割りから完成まで大丈夫。
(上の写真は竹がまだ乾いていない部分があって、緑が濃い部分が残っている)
●竹細工 そろそろ在庫がたまってきた
卒業研究指導の学生が入替り立ち代りやってる。その合間の時間でまた一つつくってみた。
今度は新しいチャレンジをしている。
●竹細工 入門は遠いが、六つ目あみは完全マスター(六つ目あみ卒業検定)
昨日つくっていたヒゴは孟宗竹のヒゴ。その前がま竹。孟宗竹はなぜかヒゴづくりが難しい。繊維が太くて堅い(竹の年のせいかもしれないが)。
そこで、ま竹と同じようにヒゴが作り易かった破竹を拾ってきた。
破竹がどんな竹で、どんなところから拾ってくるかというと、下の写真のような竹で下のような朽ちていく竹の中から拾ってくる。
破竹の正しい見分け方は知らないが、ちょっと表面に縦方向に細かい溝があり、どちらかといえば細めで、白い粉(ろうのように熱をかけると解ける)をふいている。
材質としては、やわらかく粘り気があるような気がする。

この竹をつかって6つ目編みのイメージトレーニングの成果を試すことにする。
現在の私の技術の粋を結集した。そして出来上がったのはこれまでよりも難しい技術をつかっている。
(見た目では分からないのが残念)。
拾ってきた竹を、割って、剥いで、編んで、仕上げて、だいたい4時間くらいだろうか・・・。
●竹細工 入門は遠かった・・・。
下の編み方は六つ目網というようだが、それはマスターしたと思った。しかしそうではなかった。
3つめ四つ目をつくる過程で、どうやら甘かったことが分かった。完全ではなかった・・・。
まぁ、そんなことはさておき、新しい編み方にチャレンジしてみた。これは簡単だろうと。
四つ目網だ。ひそかな希望は自分で編んだ竹かごでアサリ拾いに行くことであるので
六つ目網だと、ハマグリしか籠の中に残らない。
そこで、網目が細かい四つ目にチャレンジ。いつもどおりに
原理と原則をマスターするためにお試しをしてみたが、これが難しかった。
私はまだまだ入門レベルではないようだ。
お試し第一号 網目がめちゃくちゃだし、うまく筒にならない

お試し第二号
材料に奮発して、表皮の丈夫な素材をつかってみたが(結構本気モードだった)、表皮が堅い分(?)形を整えることができなかった。


まぁ、ミニアサリ拾いの籠ではあるが・・・。
余談
竹ひご作りではごみがたくさん出る。ビニール袋に入れて捨てればいいのだろうが
竹がビニールを突き破り怪我をする。そこではじめた頃は、腐っちまえ!と外に捨て雨に当てていただけだったが
縄文人の貝塚のように、竹ひご塚ができあがる。それは景観を悪化させていた。そのうち誰かに怒られるだろうとおもい
人を怪我させれることなく(ゴミ袋にいれて捨てることなく)、しかも景観を悪化させない方策はないものかと考えたところ
燃やすことにした。
いまでは、少したまるごとにちょっとづつ燃やすことにした。

十分に酸素が行き届けば、煙もでない。しかし、酸欠になると煙がでて
もしかしたら、近くの火災報知機を鳴らしてしまうのではとドキドキしている・・・。
(そんなときは火を仰いで酸素を送り煙をなくす)
なお、燃えカスはほとんど残らない。
●竹細工 入門レベルになりました?
先日、職場に隣町でかごやを営んでいる職人さんが授業にやってきた。
彼に細工を見てもらったら、「恐れ入りました」とのお言葉をちょうだいする。
また、竹細工をするときに、必要に応じてつくった竹ヒゴの幅を揃える道具を見せたら
刃物の角度などが理にかなっているということで、これまた関心してくださった。
それで、ちょっと気分が高潮して、初めての編み方にチャレンジしてみた。
竹ヒゴの幅を揃える道具


六つ目かごというらしい・・・。
まずは、編み方を覚えるために、ヒゴづくりで失敗したヒゴをつかって試行錯誤。

形はいびつだが、編み方は判った!
それで、まじめに作ってみた。

これはまぁ、まぁの出来。
下のかごと違って難しくないなぁ。
しかも、容量の割には竹ヒゴはあまり必要ない。
********************************
●木皮編
したの写真でバケツにつけていたサクラの皮を剥いでナタのケースの化粧をしてみた。
プロの細工師がどうやっているのか判らなかったが、昨日、化粧をするナタの合皮の化粧をヒンむいて
その細工方法がわかった。

 ←皮を剥がされたサクラ
←皮を剥がされたサクラサクラの木が落ちていたので、革を剥いでナタのケースに張り付けてみた。


********************************
●竹細工編
一代目 失敗の介

竹を割って、竹を剥いで多くの材料をつくってみた。
うえの木皮編で成功を収めた勢いで
リュックの代わりになる竹篭を作ろうとした。
なにもしらずに作り始めたら、
底部分を編んだものの
その後、この編み方ではうまくいかないことに気づく。
これ以上の改善する意欲をうしない
作品は途中で捨てた。
2代目 小篭

失敗の介をしたので、今度は失敗の過程で出てきた問題の解決法を探り
まずは、小物づくりから再トライ。
いろんな部分の竹をつかって各素材の性格もみてみた(一年もの、多年もの、表皮部分、竹の内側の肉の部分)
なんとなく判った気になった。
3代目 魚籠のような篭

なんとか、竹篭のこつはわかったような気になった。
そこで、目標の作品(リュックの代わりになる背負える篭)のミニチュアの魚籠をつくることにした。
そこで発見したものは、どうやら四角の口はとても今の自分の技術力では不可能であることをさとった。
第四代目 丸口の篭

四角の口が難しいことがわかったので、こんどは丸口でチャレンジ。
なんとかクリア。
あとは、底の部分の加工だ!
第五代目 小判型の口(オール竹:口を押さえる紐が四代目が麻・二代目三代目がツル)


丸口でなんとなく、竹の扱いが判ったきがしている。底の部分も
年末ホームセンターを探検したおかげでその加工法もなんとなく判った。
そこで、第五代目を作成した。四代目では、丸口といえども不定形に変形した丸だったが
今度は四角口の前哨戦として丸口を作成。
しかも、口を押さえる紐を竹で巻くことにも成功。
いまでは竹は、ナタが透けるほど薄く剥げるようになった。
でも、やっぱり底の部分がまだ改善のよちあり。
********************************
●木工編
子供の頃から何かをつくることが好きだった。
難しい仕組みの機械はあまり得意ではないけれど
木工なんかは、自分でゼロから完成まで全ての工程を体験できるので好きだ。


皮を剥いだクルミの幹をもらった。
フィールド調査用のヘルメットやナタをかけておくスタンドをつくった。

サラリーマン時代に夜な夜な作成した椅子。